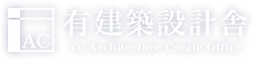雑記 ー 日記
2025/03/16(Sun)カーボンニュートラルと木造住宅
日記
カーボンニュートラルやカーボンオフセット、という言葉をよく見かけるようになりました。
とある飲食店の幟にも書かれていて、身近な言葉になったのだと思いつつも、カーボンニュートラルってなんだろう、と改めて調べてみました!

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出量と吸収量を均衡させ、地球全体での温室効果ガスの増加を防ぐ考え方、だそうです。
エネルギーの使用によって発生する二酸化炭素の排出をできる限り減らし、森林や土壌などによる吸収を促進することで、最終的に排出と吸収が相殺される状態を目指します。
二酸化炭素(カーボン)を相殺(ニュートラル)する、という事なんですね。
地球温暖化の進行を抑え、持続可能な社会を目指していく、という動きです。

木造住宅は、カーボンニュートラルに貢献しやすい建築方式のひとつと言えます。
木材は成長過程で二酸化炭素を吸収し、建築資材として使用されることで長期間にわたって炭素を貯蔵する特性を持っています。
さらに、木造住宅は断熱性に優れているため、冷暖房のエネルギー消費を抑えることができ、二酸化炭素の排出削減にもつながります。
また、森林を適切に管理し、持続可能な木材を使用することで、環境への負荷を抑えながら資源を有効活用することができます。
カーボンニュートラルな住まいを実現するためには、木造住宅の特性を活かしつつ、省エネルギー設計や再生可能エネルギーの活用を取り入れることが重要です。
例えば、高性能な断熱材や省エネ型の設備を導入することでエネルギー効率を高め、太陽光発電などを活用することで化石燃料の使用を減らすことができます。
こうした工夫を積み重ねることで、環境負荷を抑えながら快適な暮らしを実現することが可能になります。
さらに、木造住宅の場合、解体をする場合においても、再利用可能な部材が多かったり、自然分解可能な部材が多かったりする事もあり、環境負荷を下げる事が可能と言われています。
2025/03/14(Fri)三寒四温
日記
冬の寒さが和らぎ、春の訪れを感じるこの時期「三寒四温」という言葉がよく使われます。
これは、寒い日が三日続いた後、暖かい日が四日続くという気候の変化を表した言葉で、もともとは中国北東部や朝鮮半島の冬の気候を指していました。
しかし、日本でも春先の気候に似た現象が見られるため、季節の移ろいを感じさせる表現として定着しました。
木造住宅に住む人々にとっては、家の温もりや調湿性が心地よく感じられる時期でもあります。
木の家は、寒暖の差が大きいこの季節にこそ、その良さが際立ちます。
木造住宅には「調湿性」という大きな特長があります。
木は湿気を吸収したり放出したりする性質を持ち、室内の湿度を適度に保つ働きをします。
無垢材を使用した空間は、パキパキ、と時折音がなり、素材が生きている事を実感します。
冬の乾燥した日には湿気を放出し、逆に雨の日や湿気の多い日には吸収するため、快適な環境が保たれます。
これは、三寒四温のように寒暖差が激しくなる時期には特に有効で、体への負担を和らげる効果があります。
また、木造住宅は断熱性にも優れています。
木自体が持つ断熱性能に加え、木の家では伝統的に土壁や漆喰などの自然素材を使うことが多く、これらもまた温度変化を和らげる効果を持っています。
朝晩は冷え込み、日中は暖かくなる三寒四温の時期でも、急激な気温の変化を和らげ、心地よく過ごせます。

寒い日が続くと、無意識のうちに温もりを求めるものです。
木造住宅は、木が持つ自然な温かみや肌触りの良さによって、視覚的にも触覚的にも安心感を与えてくれます。
たとえば、フローリングが無垢材であれば、冬の朝に裸足で歩いたときの冷たさが軽減され、木の温もりを直接感じることができます。

三寒四温が繰り返されるこの時期、木造住宅に住む人は、その特性をより一層活かすことができます。
例えば、窓を開けて自然の風を取り入れ、木の調湿作用を助けることで、さらに快適な室内環境を作ることができます。
また、湿度調整に優れた無垢材の家具や、畳のある和室などを活用するのも良い方法です。
木の家は、ただの住まいではなく、四季の変化を感じながら、自然と調和して暮らすための場でもあります。
三寒四温の移り変わりを楽しみながら、木の温もりに包まれた快適な生活を送ってみてはいかがでしょうか。
2025/02/25(Tue)建築基準法が変わります!
日記
2月の終わりが近付いてきて、春の訪れが待ち遠しいこの頃ですが、この4月、建築業界では大きな変化があります。
2025年4月、建築基準法改正です。

(画像は記事と関係のない弊社設計物件です。)
1. 省エネ基準適合の義務化
すべての新築建築物に対して、省エネ基準への適合が義務付けられます。これにより、建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査が行われ、適合しない場合は確認済証や検査済証が発行されません。
2. 建築確認・検査対象の見直し
木造建築物に関する建築確認や検査の対象範囲が変更されます。特に、これまで審査が省略されていた「4号特例」の対象範囲が縮小され、より多くの建築物が詳細な審査の対象となります。
3. 構造計算が必要な木造建築物の規模変更構造計算が必要となる木造建築物の規模が見直され、2階建て以下の木造建築物で、延べ面積が300㎡を超えるものが対象となります。
4. 大規模建築物における防火規定の変更大規模な木造建築物に対する防火規定が見直され、耐火性能の基準が強化されます。
5. 既存住宅の改修に関する規定
既存の木造戸建住宅における大規模なリフォームが建築確認手続きの対象となり、適切な手続きが求められます。
特に木造建築物への影響が大きい今回の改正では、住宅の建築に大きな影響を与えると予想されます。
住宅の設計では、、建築確認申請書というものを行政や審査機関に提出しますが、その申請書の審査に一時的に長い時間がかかる様になったり、審査機関が一時的に閉鎖する事もあります。
設計から建設へ進む段階の方には大きな影響がある場合もあります。
ゆとりを持った設計計画を立てられることをオススメします!
カテゴリー
アーカイブ
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月